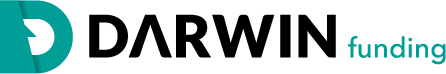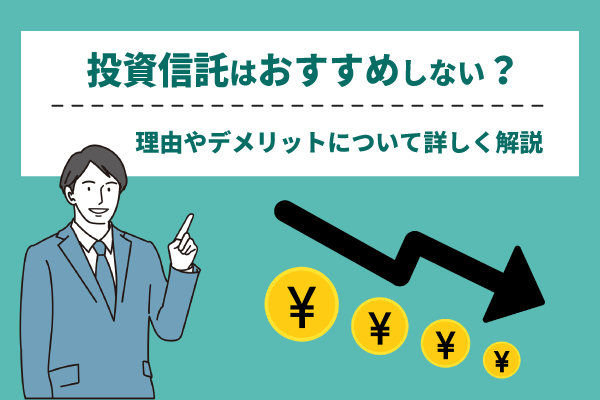ブログ記事
「投資信託はおすすめしないといわれる理由は?」
「投資信託が向いていない人の特徴は?」
投資信託は初心者でも手軽に資産運用を始められる投資方法の一つですが、「おすすめしない」と言われることもあります。
本記事では、投資信託の仕組みやデメリットを詳しく解説し、どのような人に向かないのかを解説します。
また、投資信託に代わる選択肢も合わせて紹介します。
最後までご覧いただき、自分に合った投資方法を見つけるための参考にしてください。
投資信託の仕組み
投資信託とは、多くの投資家から集めた資金を運用のプロ(ファンドマネージャー)が管理し、株式や債券などに投資する仕組みです。
個人で投資するよりも分散投資ができるため、リスクを抑えながら資産運用ができるとされています。
投資家は投資信託を購入することで、そのファンドの運用成果に応じた利益を受け取ることが可能です。
しかし、ファンドによって手数料がかかることや、必ずしも高いリターンが得られるわけではない点に注意が必要です。
投資信託には多くの種類があり、リスクやリターンのバランスも異なります。
そのため、自分の投資目的やリスク許容度に合ったファンドを選ぶことが重要です。
「投資信託はおすすめしない」と言われる理由
投資信託は多くの投資家に利用されていますが、一方で「おすすめしない」という意見もあります。
その理由には、主に以下の5つが挙げられます。
- 手数料が高く運用コストが利益を圧迫する
- 市場平均を下回る運用成績のファンドも多い
- 投資対象が不透明でリスク管理が難しい
- 元本保証がなく損失リスクがある
- 長期投資向けだが途中解約のデメリットが大きい
それぞれの理由について、以下で詳しく見ていきましょう。
手数料が高く運用コストが利益を圧迫する
投資信託にはさまざまな手数料がかかり、運用コストが利益を圧迫する要因となります。
主な手数料は、以下の通りです。
- 購入時手数料
- 信託報酬(運用管理費用)
- 売却時手数料
特にアクティブファンドの場合、信託報酬が高額になりやすいです。
例えば、年1.5%の信託報酬がかかる場合、10年間運用すれば手数料だけで15%の資産が減る計算になります。
市場の成長率がそれ以上でなければ、実質的な利益は少なくなります。
インデックスファンドなどの低コストな商品もありますが、それでも一定の手数料は発生するため、コストを重視する人にとっては不利な選択肢となる可能性があります。
市場平均を下回る運用成績のファンドも多い
投資信託の中には、市場平均を上回るリターンを目指すアクティブファンドがありますが、実際には市場平均を下回る運用成績のものも少なくありません。
特に高い手数料を取るアクティブファンドの場合、運用コストが利益を圧迫し、市場全体の成長率を下回ることがよくあります。
モーニングスターの報告によれば、日本のアクティブファンドのうち、1年以内で市場平均を上回ったのは約36%でしたが、3年では24%、5年で27%、10年で14%、15年で約20%と、期間が長くなるほどその割合は低下しています。
参考:Japan active funds, like global peers, underperform passive rivals
また、ファンドマネージャーの運用判断による影響も大きく、短期間で成績が変動しやすい点もリスクの一つです。
投資対象が不透明でリスク管理が難しい
投資信託は、投資家から集めた資金を複数の銘柄に分散投資するため、一見するとリスクが抑えられているように見えます。
しかし、どの銘柄にどの程度投資されているのかがリアルタイムで分かりにくく、投資対象の透明性が低い点がデメリットです。
投資信託の透明性はファンドによって異なり、定期的に運用レポートを公表するものもありますが、アクティブファンドでは投資方針の変更により、投資対象が変動することもあり、リアルタイムでのリスク管理が難しい場合があります。
また、一部のファンドでは仕組みが複雑で、実際のリスクが見えにくいケースもあります。
市場の急変時には、ファンドの構成銘柄が大きく影響を受ける可能性があるため、リスクをしっかり把握した上で運用を考える必要があります。
元本保証がなく損失リスクがある
投資信託は元本保証がないため、市場環境によっては投資した金額を下回る可能性があります。
特に株式を中心に運用するファンドでは、市場の急落により資産価値が大きく減少するリスクがあります。
また、債券型ファンドでも、金利上昇の影響を受けて価格が下がることがあります。
投資信託はプロが運用するとはいえ、必ず利益が出るわけではなく、状況によっては大きな損失を抱えるリスクがある点を理解しておくことが必要です。
長期投資向けだが途中解約のデメリットが大きい
投資信託は基本的に長期運用を前提とした商品ですが、途中解約には大きなデメリットがあります。
まず、多くの投資信託では解約時に「信託財産留保額」や売却手数料が発生し、元本が目減りする点がデメリットです。
また、基準価額は日々変動するため、解約のタイミングによっては想定よりも少ない金額しか受け取れないことがあります。
特に市場が急落した際に焦って解約すると、大きな損失を被る可能性が高まります。
さらに、分配金を再投資するタイプのファンドでは、途中解約によって複利効果が得られにくくなる点もデメリットです。